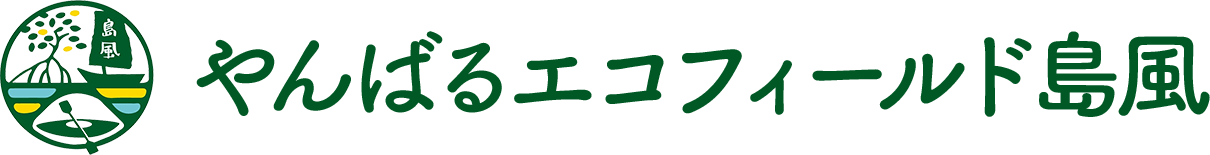沖縄の伝統木造船「帆かけサバニ」造船REPORT③
目次
沖縄の伝統木造船「帆かけサバニ」造船REPORT③
水にぬらして、8mの木材を曲げる準備

2017年6月13日
舷側板の左右が、正確に同じ形でも、自然の木の素材ですから、水分量、フシの位置など、様々な理由で柔らかさは同じではありません。
そのため、同じ形を曲げても、左右対称の船の形を作ることは本当に難しいことなのだそうです。
曲げ終わるまでどのくらいかかるかは、自然の材料なので、やってみないとわからないそうですよ。
一晩、板の中に水を貯めて、曲げの準備。
木の様子を見ながら、少しずつ曲げる

2017年6月14日~21日
割れがはいらないよう、ていねいに、集中して広げていきます。時間の経過とともに、何cmになったのかをきちんと記録にとり、木の自然な動きを調べます。自然の材料である木は、ひとつひとつ固さ、柔軟性、伸縮性、様々なことが違います。育ったところが、山の上なのか、谷なのか。周りはどんな森だったのか。いろんな条件が、ひとつの木の状態を決めていくのです。それを見極めて、動きを観察して、曲げていきます。
「(木の)こんな動きが見られてきたから、次は、この場所をこうしてみる。」
と大工さんは考えながら、作業を決めていきます。曲げる力も、曲げる場所の順番も、考えて形を作ります。
それは、板に緊張と張りをもたらし、板に強度が生まれます。それが、船として生まれたとき、乗る人たちの安全につながるのです。…
「今回の材木は、今まで作ってきた材木と比べてどうですか?」
と、質問すると、大工さんの長嶺さんは、
「かたい。」と一言。
それだけ、曲げる作業は難しくなる。時間がかかる。しかし、それだけ強度があるということなので、安全で、よい船になるということ。
そんな風に語っていました。一歩ずつ、ゆっくりと。木の声をききながら作業をしていきましょう。
何時間もかけて、少しずつ、少しずつ、水をかけながら数センチずつ。ここっ!という箇所で、板と板の感覚を絞り、ひねりを付けていきます。まっすぐな板だったことが信じられませんね。こうして曲げることで、舷側板が緊張した状態を作り、強度が生まれます。
絞りを入れていくと、様々な箇所で、「動き」が見られてきます。あ、こっち側が上がってきた。あ、広がってきた。膨らんできた。あ、前後が縮んできた。
それを敏感に感じ取らなければなりません。
メジャーで測ればわかるポイントもあれば、
じーっと目でみて観察し、チェックすることも。
ほんとにわずかな動きです。サバニ大工の腕の見せ所といった感じでした。すばらしい。
修正が必要な場合の「動き」なら、そこでまた、手を加えます。
完成。。。。パチパチパチ。曲げが終わったとき、拍手してしまいました。
形を固定するため、横木を入れる

2017年6月22日
「曲げ」作業が終わって、サバニの形が決まったので、横木を入れました。形を固定するためです。その後は、スクジーという、船底部分の製作に入ります。そこでついに登場するのが、樹齢約80年といわれる厚く、重い材木。これが、サバニの「本ハギ」と呼ばれる作り方の大きな特徴。底板はかなり厚い材木で、くり抜くようなイメージで形を作っていきます。
これは、男性でも、一人では持ち上げることができません。それを、サバニの上に持ち上げ、のせて、どこを削るのかを目で確認し、降ろして、削る。また、持ち上げる。これを何回も何回もしなければなりません。
完成した帆かけサバニ「島風」に乗ってみたい方はこちらから👇
メールでのご予約・お問合せはこちら

やんばるエコフィールド島風(しまかじ)
【マングローブカヤック・ナイトマングローブカヤックのご予約】
①ご希望の日のツアースタート時間を下記にて確認し、
②下記「お問い合わせフォーム」、またはお電話にてお問合せください。
↓
③空いていれば、予約完了のメールを送ります。空いていなければ、その旨と、ご希望の日の前後の空き状況を書いて返信をします。
【帆かけサバニ・シャワークライミングのご予約】
①下記「お問い合わせフォーム」、またはお電話にて「ご希望日」をお知らせください。
↓
②ガイドに空きがあれば、「ツアースタート時刻」を書いて、弊社から返信します。空いていなければ、その旨と、ご希望の日の前後の空き状況を書いて返信をします。
↓
③ご予約されるかどうかの返信をお客様からお願いします。
↓
④予約完了のメールを弊社から送信。
※24時間たっても返信がない場合は、受信設定などの理由で、弊社からのメールが届いていない可能性があります。
※予約ではなく、空き状況のみのお問合せもお聞きしますが、「予約する」というご連絡を受けてからのみ、お席の確保となりますため、お問合せ後、空き状況は随時変動していきますことをご了承ください。
カヤック2h → マングローブカヤック2時間
カヤック3h → マングローブカヤック3時間
N → ナイトマングローブカヤック1時間半
電話でのお問い合わせはこちら
電話受付時間:8:00~20:00
※年中無休ですが、弊社ではツアーガイドが電話対応をしているため、
ツアー中は電話に出られないこともあります。
その場合は、上記の問い合わせフォームをご記入、送信をお願いします。
前の記事へ
次の記事へ